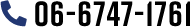こんばんは、福田です。
今日も、今日は何の日シリーズです 

バレンタインデー
2月14日は聖バレンタイン(ウァレンティヌス)の命日だから。
西暦3世紀ごろのローマ帝国では「妻や子どもがいると兵士たちの士気が下がる」という理由で結婚が禁止されていた。
それをかわいそうに思ったキリスト教の司祭「バレンタイン」は隠れて兵士たちの結婚式をおこなっていたのだ。
それが皇帝の耳に入ってバレンタインは処刑されてしまうのだが、
皇帝の命令に屈することなく恋人たちを結婚させた彼の名にちなんで命日は恋人たちの日「バレンタインデー」となったのだ。
バレンタイン=チョコレートは日本だけ?
日本でバレンタインデーといえば、女性が男性にチョコレートをおくるのが一般的だが、これは日本独自の習慣である。
欧米では恋人や親しい人にメッセージカードを添えたプレゼントや花束をおくるのが一般的なのだ。(チョコをおくることもある)
そのうえ、日本とは反対に男性から女性へプレゼントをすることのほうが多い。
というのも、男性がお返しをする「ホワイトデー」は日本独自の習慣なので欧米には存在しないのだ。
そのうえ、日本とは反対に男性から女性へプレゼントをすることのほうが多い。
というのも、男性がお返しをする「ホワイトデー」は日本独自の習慣なので欧米には存在しないのだ。
バレンタインにチョコレートは誰がはじめた?
いろいろな説があるが、洋菓子メーカーの「モロゾフ」が
1936年の2月12日に「あなのたの愛しい方にチョコレートを贈りましょう」という広告を新聞に出したのがはじまりだといわれている。
1936年の2月12日に「あなのたの愛しい方にチョコレートを贈りましょう」という広告を新聞に出したのがはじまりだといわれている。
他には、1958年の2月12日にメリーチョコレートが伊勢丹で「バレンタインセール」という看板を出してハート型のチョコレートを販売したのがはじまりだという説もある。
1年目は3日間で3枚、170円しか売れなく、当時は、バレンタイデーにチョコという習慣はなかな定着しなかった。
1年目は3日間で3枚、170円しか売れなく、当時は、バレンタイデーにチョコという習慣はなかな定着しなかった。
多くのチョコレート会社やお菓子メーカーが「バレンタインデーにはチョコレートを」という販売戦略を進めた結果、
1970年代にチョコの売上が上がり、1980年代にバレンタイン=チョコが定着したといわれているのだ。
現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となった。
1970年代にチョコの売上が上がり、1980年代にバレンタイン=チョコが定着したといわれているのだ。
現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となった。
一箇月後の「ホワイトデー」に返礼のプレゼントをする。
チョコレートの日
2月14日がバレンタインデーであることにちなんで、切っても切れない関係である「チョコレートの日」となったのだ。
板チョコに溝があるのは、なぜ?
板チョコに溝があるのはチョコを割りやすくするためではない。
チョコレートを冷やすとき、チョコと型の接する面積が多いほうが早くチョコを固めることができるので溝のある型をつかっているのだ。
それと、溝があったほうが型から取りだしやすいからなのだ。
それと、溝があったほうが型から取りだしやすいからなのだ。
チョコの包み紙にアルミ箔が多い理由
チョコレートがアルミ箔(はく)で包まれているのはチョコの香りを守るためである。
チョコレートはニオイを吸着しやすいので、他の食べ物のニオイがうつるのを防ぐために空気を通しにくいアルミ箔で包まれているのだ。
また、アルミ箔は光りを反射するので、熱でチョコレートがいたんでしまうのも防いでくれている。
チョコレートはニオイを吸着しやすいので、他の食べ物のニオイがうつるのを防ぐために空気を通しにくいアルミ箔で包まれているのだ。
また、アルミ箔は光りを反射するので、熱でチョコレートがいたんでしまうのも防いでくれている。
もうこの歳になると、バレンタインなんてなんら普段と変わらないただの日常と化してしまう…

ちなみに、はじめてバレンタインにチョコを渡したのは、小学校3年でした。
当時は学校にチョコなんて持って行けなかったので、放課後友だちと一緒にその子の家まで行って渡しましたね~ 

お返しには、マシュマロ(今時、無いやろね… )を頂きましたね!
)を頂きましたね!
 )を頂きましたね!
)を頂きましたね!渡された時の一言『お母さんに持って行けって言われたから…』でしたわ

あ今日、社長のおくさんから社員みんなに、バレンタインデーやし、とチョコを頂きました 

おやつに、頂きました! 甘くて美味しかったです 

バレンタイン…関係にゃいニャー